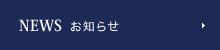- ホーム >
- 研究関連 >
- 試料の利用を伴うデータ利用申請 >
- 真性多血症、骨髄線維症、本態性血小板血症の遺伝子異常と予後との関連の検討
真性多血症、骨髄線維症、本態性血小板血症の遺伝子異常と予後との関連の検討
研究の目的
近年のゲノム・エピゲノム研究が活発に行われるようになり、多くのがんにおいてゲノムやエピゲノムの異常が臨床に役立つ指標として臨床現場で活用されてきています。造血器腫瘍においても1,540例の急性骨髄性白血病(acute myeloid leukemia: AML)に対するシーケンス結果と予後との関連が報告されています。また近年骨髄異形成症候群(myelodysplastic syndromes: MDS)に関しても変異の情報を予後予測に盛り込んだ予後分類が提唱され、変異情報がAML、MDSの予後に与える影響は数多く報告されています。
そのような中で原発性骨髄線維症、本態性血小板血症、真性多血症における高頻度に認めるJAK2、CALR、MPLにおけるhotspot変異が強力なドライバー変異として知られ、それに付加的な遺伝子変異が加わっていき病態の進展に関与すると考えられています。これらの疾患への治癒が期待できる治療法は同種造血幹細胞移植のみですが、他造血器腫瘍と比較し予後良好であるので、進展したリスクの高い患者さんに同種造血幹細胞移植という治療法が選択されます。しかし罹患年齢が高齢である場合は原疾患以外のご病気を持つことも多く、治療自体の毒性による影響も懸念されます。AMLやMDSと比較し移植が行われる件数は少ないですが、だからこそ全国規模のデータと変異プロファイルを合わせ、予後の改善につながる研究が必要と考え本研究を立案しました。
研究の方法
本研究では、2006 年 4 月から 2021 年 12 月までの移植を受けた患者さんの内、日本造血細胞移植データセンター/日本造血細胞移植学会の実施する「造血細胞移植および細胞治療の全国調査(R1343)」及び「非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植における検体保存事業(G1026)」の研究計画に同意いただいた試料及び診療情報を利用します。試料については、京都大学大学院医学研究科腫瘍生物学講座にて次世代シークエンス(Next generation sequencing:NGS)を用いて造血器腫瘍において高頻度で認める遺伝子変異やコピー数異常を解析します。これらの解析結果と診療情報を用いて、京都大学大学院医学研究科血液内科学教室にて移植成績に関する解析を行います。
研究実施期間
研究機関の長の実施許可日から2028年12月31日
研究計画書
- 研究計画書(ダウンロードいただくには、JDCHCT HP のWeb認証が必要です。)
倫理審査結果通知書
- 許可書_京都大学(ダウンロードいただくには、JDCHCT HP のWeb認証が必要です。)
研究組織
<研究代表機関>京都大学医学部附属病院 血液内科
研究責任者 講師 諫田淳也
個人情報について
全ての検体は、研究用のコード番号で管理し、ご提供いただいた方の個人情報が研究利用の段階で漏えいすることがないよう管理されます。個人の診療情報についても同様に、個人情報が保護される様に注意して管理されます。
問い合わせ先
京都大学大学院医学研究科 血液内科学講座 諫田淳也
(Tel) 075-751-4964 (E-mail)jkanda16@kuhp.kyoto-u.ac.jp